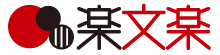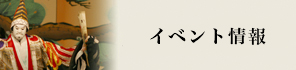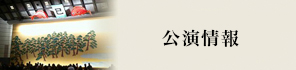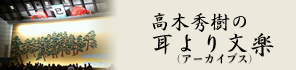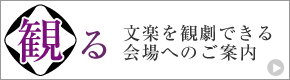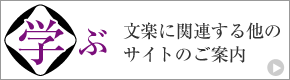吉田簑助 不屈の闘志で舞台にカムバックした人形遣い!
2013年1月11日更新
平成10年11月、仮名手本忠臣蔵の公演中に脳出血で倒れ、不屈の闘志で翌夏の公演で舞台復帰した文楽人形遣いで人間国宝の吉田簑助。文楽と半生についてインタビューした。
吉田簑助
*********************************************************************************************
1933(昭和8)年、大阪市生まれ。父は二代目桐竹紋太郎。1940年に吉田文五郎に入門。1948年、桐竹紋十郎門下に。1961(昭和36)年、三世吉田簑助を襲名。1994(平成6)年、重要無形文化財保持者(人間国宝)認定。紫綬褒章、日本芸術院賞など多数受賞。2010(平成22)年、文化功労者に。2012(平成24)年、芸術院会員となる。1998(平成10)年11月公演中に脳出血で倒れる。翌年の夏公演で舞台に復帰。2007(平成19)年、フランス政府より芸能文化勲章
**********************************************************************************************
公演中楽屋で倒れ、八ヶ月後復帰
パリのルーブル美術館での特別上演の翌年、簑助はアムステルダムにいた。アムスでの公演が終了し、現地の記者から「またオランダへ来てくれますか」という問いに、頭を傾げて少し間をおき、「生きてたら・・・」とゆっくりしたテンポの茶目っ気ある笑顔で答えていたのが印象に残る。長時間のフライトや慣れない劇場で人形を遣う海外公演は想像以上に体力を消耗する。周囲はことのほか簑助に気を遣う。
その10年ほど前の11月、文楽大阪公演の二日目。仮名手本忠臣蔵は七段目の由良之助とおかるの名場面。終了後、風呂場の脱衣場で簑助は倒れた。脳出血だった。そして、舞台の復帰を目指して過酷で気の遠くなるリハビリに耐えた。そして、奇跡的に人形を遣えるまでになった簑助は8月の大阪の舞台で復帰した。
自ら選んだ人形遣いへの道
あれから14年。今年、傘寿を迎える簑助に、体調を問うと、「まあ、ぼちぼちと言ったところです」という答えが返ってきた。文楽の世界に入り74年がたった。昨秋、芸術院会員に選出された。文楽の長い歴史の中でも輝かしい功績である。父親が人形遣いだったことから、自ら文楽人形遣いになった。
「父が桐竹紋太郎という人形遣いでした。ごく小さい頃から父について四ツ橋の文楽座に通い、何をするという訳でもなく楽屋中をちょこまかしていましたので、ごく自然に、自分も人形遣いになるものと思っていました。ただ時代も戦争が暗い影を落とし、文楽はあと10年もすれば潰れて無くなると思われていた時代ですから、父は大反対でした。が、どうしても人形遣いになると駄々をこね、ねばり勝ちして人形遣いの道を歩みはじめました。六歳の時のことです」
父親に反対されても、小さい体で父親の足遣いをこなすのは、文楽が簑助にとって生きる証だったのかもしれない。
長く厳しい修行の世界
父の本名から一字をもらい、小辰と名乗り、介錯や足遣いの手伝いをしていた。7歳で吉田文五郎に入門し、桐竹紋二郎となる。
文楽の人形は一体の人形を人形遣いが3人で遣う。世界に人形芝居は数多あるが、三人遣いの形態をなすのはこの文楽だけ。世界に類を見ない人形芝居なのである。人形であるからこそ、緻密な動きが求められる。人形の首(かしら)と右手を遣い全体をリードする主遣いになるまでには、足遣いを10年、左遣いを15年、最低でも25年という長い修行が必要となる。
「私の修業時代と言えば戦争中で、今の時代から隔世の感がありますが、足を遣っていて出来が悪かったりすると、小道具の杖で叩かれたり、舞台下駄で蹴られたり、そんなことは日常茶飯事でした。しかしそれも、修業の上の愛のムチ、感謝して励みにこそすれ、根に持って恨むということは有りませんでした。しかしある時、小道具の刀を忘れたということで、主遣いの人から平手で顔を叩かれました。その様子を舞台の反対側で見ていた父が、切ない情けない表情をしたのが子供心に辛くて、叩いたこの人の上に立つ人形遣いにならねば、と思ったのを鮮明に覚えています。嬉しかったことはありますが、おもしろかったことはありません」と簑助は語る。
曽根崎心中、吉田玉男と
良い意味での人の上に立つ、その意識が技術の習得、時代の変化に伴う工夫をもたらし、人形の表情や所作が一体となって観客へ感動を与えられる。
 2001年5月、文楽公演が行われている東京三宅坂の国立劇場で輝かしい出来事があった。吉田玉男が「曽根崎心中」の徳兵衛役を通算1000回目に到達、という大偉業である。玉男が50年にわたり徳兵衛を遣い、相手役であるお初の役を、簑助が30年もの間遣い続けたのである。
2001年5月、文楽公演が行われている東京三宅坂の国立劇場で輝かしい出来事があった。吉田玉男が「曽根崎心中」の徳兵衛役を通算1000回目に到達、という大偉業である。玉男が50年にわたり徳兵衛を遣い、相手役であるお初の役を、簑助が30年もの間遣い続けたのである。
玉男の人形には命があるとさえ言われたほど、繰り返し登場人物の性根を研究し新しい解釈を加えていった不世出の人形遣いだ。2006(平成18年)9月24日、惜しまれつつこの世を去った。玉男は長い間、人形遣い、ひいては文楽を牽引してきた。仮名手本忠臣蔵での大星由良之助の彫りの深い解釈と表現は上品でかつ重厚で、その演技は今なお語り継がれている。命日となった9月24日は東京で仮名手本忠臣蔵の通し狂言が行われていて、ちょうど千秋楽でもあった。一年以上休演していた玉男に代わり立役の最高峰と言われる由良之助に遣ったのは、由良之助を40数年ぶりに遣うという簑助であった。重責の中で千秋楽を迎え、無事に由良之助を務めあげた日に、玉男逝去の悲報が楽屋へ舞い込んだ。「玉男兄さんが見守ってくれていた」、と簑助は言葉を詰まらせた。
「玉男さんとは、曽根崎をはじめとして本当に様々な役で共演させていただきました。恋人、夫婦、親子、主従、殺す者と殺される者…、心中物では千回以上は一緒に死んだはずです。しかし、私生活では、全くと言っていいほど交流はなく、一緒にお酒を飲んだ記憶もなく、それでも舞台ではぴったりと心が通いあい、心に残る舞台の相手役は、すべて玉男さんでした。不断の努力もされていましたが、100年に一人出るか出ないかの天賦の才に恵まれた人形遣いであったと思います」
三位一体の芸術、その真髄
自分の技術だけでは成立しないのは伝統芸能の中でも歌舞伎や能楽もしかり、文楽だけではない。特に文楽は、一体の人形を三人で遣う。しかし、床と呼ばれる上手の小さな舞台で物語を語る太夫、そして伴奏と劇的効果を伝える三味線弾きの存在なしには、文楽は語れない。この、太夫、三味線、人形の三業の息があってこそ記憶に残る舞台ができあがる。すべてが一体化した素晴らしい文楽の舞台は、一生に何度も見られるものではなく、長い修行と息を通わせる技量が一致したとき、出会えるのだ。三業の一致が一期一会を完成させる。
「三業のイキがぴったり合った上、舞台と客席も一つになった空気が肌にひしひしと伝わって来る…千秋楽の日が来なければいいのにと思えるほどの感動…そんな舞台は今までに数えるほどしかありませんでしたが、全ての苦労が報われるような、そのような体験がこれからも出来れば良いなと思います」
簑助に手のひらをみせてもらった。手も指も長いのが印象的だ。人形使いは左手で首(かしら)を、正確にいうと首からつながる胴串(どぐし)を握って人形全体を支える。そのため、手のひらには皮膚の硬くなった箇所がいくつかできる。簑助の弟子である桐竹勘十郎の手のひらにできた位置とは明らかに違っていた。以前、首と胴の関係性を調べたとき、いくつかの発見があった。同じ台詞であっても、人形遣いの腕の長さ、指の長さ、身長や体型によって、微妙に動きが異なる。師匠が弟子に技術を教えるのは大切だが、体型が異なれば、伝え方も異なってくる。それ以上に自ら習得しなければ役の性根までは理解できない。一つの言葉では伝えられない。弟子や後輩が、師匠の言動を長い年月をかけてこなしていくしかない、それが文楽の伝承ともいえるのかもしれない。
お弟子さんや若い技芸員には、「日々の舞台が修業の場。もっともっと舞台を見ておくように」と簑助はいう。文楽だけではなく、歌舞伎やそのほかの伝統芸能に触れることで解釈する幅も広がろうというもの。そして、自分のものになっていくのだ。
傘寿を迎える今年。それでも、簑助の新しい役への意欲は衰えていない。新たに挑戦してみたい役は?と尋ねると、「ありますが、、、秘密です」と返ってきた。筆者は10数年前にも同じ質問をしたことがあるのだが、その時は”女形”ではなく”立役”だった記憶がある。しかし、それも秘密にしておこう。
存続の危機に立たされた文楽は必ず残る
 昨年、文楽は大きな岐路に立たされた。橋下大阪市長による「文楽への補助金カット」に端を発した問題である。戦前戦後を通じて、文楽は危機状況が続いていた。特に戦後になり、そうでなくとも技芸員が不足しているにもかかわらず因会と組合派の三和会、二つに別れて興行を行っていた。運営していた松竹は文楽を手放すことを決断し、国と大阪市などが協議し、財)文楽協会を作った。国立文楽劇場(日本芸術文化振興会)が興行し、協会は技芸員を派遣する。技芸員は個人事業主である。そこへ、降って湧いたような協会への補助金カット発言である。本年度は、予定していた5000万円ではなく3900万円の至急で決着。ただし、来年度は補助金にインセンティブ方式を提示している。9万人の観客数の維持を満たすことが最低条件で、それ以下であれば支給は“ゼロ”。105,000人以上なら2900万円を後払いで支給するという。
昨年、文楽は大きな岐路に立たされた。橋下大阪市長による「文楽への補助金カット」に端を発した問題である。戦前戦後を通じて、文楽は危機状況が続いていた。特に戦後になり、そうでなくとも技芸員が不足しているにもかかわらず因会と組合派の三和会、二つに別れて興行を行っていた。運営していた松竹は文楽を手放すことを決断し、国と大阪市などが協議し、財)文楽協会を作った。国立文楽劇場(日本芸術文化振興会)が興行し、協会は技芸員を派遣する。技芸員は個人事業主である。そこへ、降って湧いたような協会への補助金カット発言である。本年度は、予定していた5000万円ではなく3900万円の至急で決着。ただし、来年度は補助金にインセンティブ方式を提示している。9万人の観客数の維持を満たすことが最低条件で、それ以下であれば支給は“ゼロ”。105,000人以上なら2900万円を後払いで支給するという。
松竹が運営を手放した時代に立ち返り、文楽を運営する関係性を、芸術文化の視点から捉えることこそ行政の本質であるはずなのに、インセンティブ方式を提示するとは、あまりにも発想が貧しすぎる。無形文化遺産である文楽を、大阪の誇る伝統文化であるはずなのに。
「私のように、昔風の修業をしてきた者が居なくなれば、文楽はまた一段と変わってゆくことでしょう。変わることは悪いことではないし、どんな将来が文楽を待ち受けているのか、それは私にも分かりません。形を変えながら、残ってゆくのでしょうね」
何があっても文楽は残さなければならない。有形無形にかかわらず、文化というものは先達の喜びや悲しみ、苦しみが、長い年月を通して今の形に作り上げてきた歴史であり、人間そのものだからだ。大阪の文化遺産であり、日本の文化遺産であり、世界の文化遺産でもある。継承していくことこそ、使命なのである。
生まれ変わっても文楽の人形遣いに
平成25年2月の文楽東京公演では、簑助は関取千両幟の“おとわ”を遣う。
「この役を遣うのは、本公演では20年ぶりでしょうか。思い出と言えば、父が亡くなって一ケ月後に、今はもう無い大阪の三越劇場でこの役を遣いました。舞台に立っている間中、父がずっと見守ってくれている…そのような感覚に包まれながら、この役をつとめた思い出があります」。
「文楽の世界しか知りませんので、生まれかわっても私はやはり人形遣いになりたい」。
生まれ変わっても人形遣いに・・・、我々には理解できない大きくて深い意味がある。文楽のような厳しい修行を経験してきた者にしかわからない、胸が詰まるのような重い言葉といえよう。惜しまれつつ引退をした竹本越路大夫が「修行は一生では足りなかった。もう一生ほしかった」と引退にあたり残した言葉を思い出し、簑助の芸への執念や修行の奥深さを改めて感じる。
簑助師匠に初めてお会いしてから30年ほどになる筆者。お弟子さんたちに自らの技術を懇切丁寧に教えている場を見たこともなければ、怒るところも見たことがない。技術は自分で会得し、高めていく。文楽特有の世界感がそこにある。
最近は体調に気遣われているのか、お酒は控えておられるようですが、お話をしているときの茶目っ気たっぷりの表情は嫌味がなく、かわいいのです。これからも体を労わりながら、舞台で活躍してほしいと願うばかりだ。
※写真の無断転載はお断りいたします。